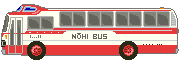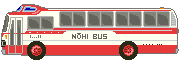1 転用する意味
貸切事業車を乗合事業用に転用することは、バス事業各社で行われています。一般的には、貸切用としてのアコモデーションは陳腐化しているが、経年的には乗合用として十分用途に耐える場合に、資産の有効活用の面から行われていると考えられます。
転用に際しては、乗合用機器(ワンマン対応機器など)の取付け等最小限の改造によるものから、乗降扉の増設を伴う等の大掛りな改造を行うケースもあります。
最近では、貸切車の「ハイデッキ」化や「バリアフリー法」の施行などにより、扉増設などの大きな改造をするよりも、最小限の改装の上高速路線や空港連絡路線など比較的距離があり旅客の乗降機会が少ない路線への転用のケースが多くなってきているようです。
 |
| 高速車への転用車の例。29036(22-336)号で、当初は名古屋線に転用された。晩年は松本線専属車両に。現在は廃車。 |
2 濃飛バスにおける転用乗合車
濃飛でも貸切車を乗合車に転用(以下、「転用乗合車」という。)することは10年程前まではよく行われていたようです。"パノラマ55"や"パノラマアロー"などの大型貸切車に、ワンマン機器や行先表示装置取付けなどの改装を行い、外見はほぼそのままに一般路線に転用されていました。また、中型貸切車も同様の改造を受け、転用されていたようです。
これら車両は、5年程前にはほぼ姿を消しています。濃飛の路線には、高度な環境対策が必要な特殊な路線(乗鞍線、上高地線など)があり、これらのために貸切車タイプの乗合車を新製していること、貸切車側に転用に適する環境対策車がない(低公害貸切車は経年が少ない)ことなどが理由と考えられます。
 |
最近まで一般路線で活躍した元上高地仕様の貸切車"パノラマアロー"の2193号。
写真協力:けん@高岡
さま |
濃飛の現有転用乗合車は、大型車は高山高速(営)に79315(22-15)号、中型車では下呂(営)に22-329号がある程度です。前者は高速路線(新宿線以外の)に、後者は一般路線をはじめ、定期観光や下呂・中津川特急(現在は廃止)に使われています。近年は、一般路線用でも「乗合用」として貸切車タイプの車両を新製しており(これらの多くは環境対策車である)、転用はあまり行われていないようです。また変わったところでは、小型貸切車の200-11号が、丹生川村コミュニティの「宿儺(すくな)号」運用のために、料金箱の設置など転用改造に準じた改装を受けています。
3 今後「転用」はあるか
濃飛において転用が考えられる路線は、高速路線と観光路線です。ただ、両路線とも厳しい環境対応(首都圏の排ガス規制や上高地・乗鞍への対応)を課されることになるので、簡単に「転用」することはできないものと思われます。また、一般路線へも、前述の「バリアフリー法」が施行されたことにより、乗降に手間のかかる車両の投入は難しくなっています。
濃飛では、貸切タイプの低公害車両を乗合車として新製投入しており、逆にこれら車両を貸切運用に就かせることがあるようです(20492(200-92)号が顕著な例です)。車両資産の有効活用を図るのであれば、環境に配意した低公害車両で貸切・乗合の双方に運用できる車両の導入が有効で、濃飛で現在進めている車両新製は、これら考え方に沿うものとも思えます。
転用乗合車は、趣味的に見れば興味を引くことです。これが少なくなってきたことは時代の流れでしょうが、逆に今後どのような車両が増備されていくかが楽しみです。
|