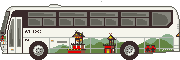
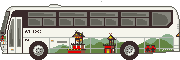 |
「濃飛 高速路線の車輌と運用」 |
○興味をひく運用 ○時刻表 ○説明 ○濃飛バスIndex ○総Indexへ戻る
濃飛の高速路線も、東京・大阪・名古屋・金沢と4路線を数えます。あのかわいい「さるぼぼカラー」の車両も7両となりました。そこで、15年春改正時点での高速運用車両とその運用を、想像をまじえながら紹介していきます。
平成15年6月に200-76が増備され、さるぼぼカラーも8両になりました。(03/06/19加筆)
![]() **内容に誤りがありましたら、管理人までお知らせください。**
**内容に誤りがありましたら、管理人までお知らせください。**![]()
[車輌]
濃飛の高速車両は、観光車両タイプの前扉車が使われています。塗色以外での高速車と観光車の簡単な見分け方は、前扉が折戸(高速車)かプラグドア(観光車)です。もちろん、続行便には観光車が充当されることがあります。高速車を分類すると、以下のとおりとなります。
[1. トイレなし車(3両)]
この分類は、以下のように細かく分類することができます。[1-1.高速線運用車両(1両)]
22-41が、現在唯一のトイレなし高速運用車です。この車両は、高山松本線の新設に伴って新造された車両で、濃飛初の「さるぼぼカラー」です。現在は、金沢線の限定運用車となっていて、車体に下呂温泉のロゴマークも入っています。なお、他の高速車両は機関出力が420PS程度ありますが、同車は350PSほどと低出力となっています。[1-2.貸切高速併用車(2両)]
22-44,200-40がこれに当たります。トイレがないので続行便への運用となりますが、新製時から降車ボタンや行先表示装置などを装備した高速仕様車です。22-44はスーパーハイデッカのプラグドア車でパノラマウィング塗色、200-40は折戸で機関出力が多少低い(370PS)車両で、塗色は貸切標準塗色です。[2. トイレ付き車(9両)]
この分類は、以下のように細かく分類することができます。[2-1.新造車(7両)]
22-43,22-52,22-53,200-16,200-39,200-52,200-76の7両が新製時からトイレ付きの高速仕様車です。これらのうち、22-53以外はさるぼぼカラーで、22-53は貸切標準色、200-16には車間距離警告装置が付いています。なお、補助席を除く座席定員は40名ですが、座席配置が通路をはさんで10+10列車と9+11列車があるほか、補助席の設置にも違いがあるようです。また、行先表示装置がLED化された車両もあり、それらの車両(と、22-53)には、運転区間を示す乗降口横の「サボ」受けがありません。[2-2.トイレ改造車(1両)]
200-33は名古屋線投入車両であったため、トイレがありませんでした。平成13年に名古屋線もトイレ付きとしたため、それに合わせて改造されました。塗色はさるぼぼカラー、座席は9+11列配置で補助席も装備されています。なお、名古屋線開設当時に貸切車両から転用された22-336は、トイレ取り付け改造を受けず、松本線に転用されました。
[2-3.転用車(1両)]
22-15が、パノラマウィング塗色のスーパーハイデッカー車として存在します。この車両は、乗降扉がプラグドアです。座席は9+11列配置です。
[運用]
[新宿線(シュトライナー)]
平成10年に濃飛初の高速路線として開業した当路線も、満5年を迎えています。夏期を除き1日4往復ずつが運転(夏期は6往復)され、京王電鉄バスと半数ずつの受け持ちとなっています。
濃飛便は、高山を午後に出て、東京で1泊して翌日の朝新宿を出て高山に帰る運用です。新宿から帰投した車両は、時間的には高山折り返しも可能ですが、1便ずつ後の便にシフトするような運用になっていると思われます。夏期以外で続行便がないときは、1日3両使用の運用ということになります。続行便を除き、トイレ付き車で運行されます。[大阪線(ウエストライナー)]
新宿線から2年遅れて開設された路線です。通年1日2往復が運行され、こちらは近鉄との共同運行で1往復ずつを受け持っています。基本的には[高山−大阪]を結ぶ便ですが、受け持ち会社で末端区間に発着場所の違いがあります。
濃飛便は、新宿線と同様に高山を午後に出て、大阪で一泊して翌日の朝大阪を出て新穂高まで営業、その後高山まで回送される運用のようです。こちらは当日中の運用充当が時間的にも難しいので、1日2両使用ということになります。なお今年の春改正前までは、濃飛便は平湯温泉発着で、大阪からの便で折り返し運用が(時間的には)可能でした(実際にそのような運用はされていなかったようですが)。こちらも続行便を除きトイレ付き車で運用されます。[名古屋線(メイヒライナー)]
平成12年に開設された路線で、濃飛・名鉄・JR東海バスの3社による協同運行路線です。冬ダイヤは1日6往復、それ以外は1日9往復の運行で、3往復(冬季は2往復)ずつの受け持ちです。濃飛担当便は、他社便と末端区間の延長や荘川停車便(冬季はない)があるなど特異な運用が特徴です。開業当初はトイレなし車両で運行されていましたが、現在では全便トイレ付きになっています。名鉄運用便には、同路線唯一の高山停泊運用があります。
濃飛便は高山地区発の午前2便と午後1便を担当し、その日のうちに高山に帰投する運用です。1両で[高山−名古屋]の1往復を担当し、1日3両使用です。今年の春改正前までは、朝の高山発第1便で名古屋へ1往復した車両が、午後の高山発便に充当されていたようです。
同路線には、車高の高い車輌(22-15,22-44)は運行されません。これは、名鉄バスセンターの車高制限によるものだそうです。←この情報は誤りです。22-15が名古屋線運用に入っているのを確認しました(03/08/01)。[金沢線(ノースライナー)]
名古屋線と同時期に開設された路線で、濃飛・北陸鉄道の共同運行路線です。1日2往復の運行で、冬季は運休します。なお、金沢便のほか、[下呂−鳩谷]便が1日1往復あるほか、一般道を利用する[高山−鳩谷]便が1日3往復あります。名古屋線同様、他社運行地域での停泊はありません。
濃飛便のうち金沢便は、下呂を午前に出て、その日のうちに下呂に戻る運用で、1日1両使用です。また、鳩谷便も下呂を午前に出て、その日のうちに下呂に戻りますが、帰りの[高山−下呂]は各駅に停車します。この路線は、トイレなし車が充当されており、さらに[下呂−鳩谷]便には乗合塗色の車両が使用されています。これらの車両は下呂営業所の担当です。
ご覧いただいたとおり、新宿線と大阪線では他社管内での停泊があります。これは、片道の運行時間が比較的長く、昼間に自社運行地域内で折り返すのであれば、当該便が道路状況などで遅延しても折り返し車両の確保が容易であることが理由の一つであると考えられます(名鉄折り返し便は、このような理由ではない)。高山で折り返す(停泊を含む)他社車両は、濃飛の高山車庫で折り返します(松本線は高山BCの駐車場で折り返しているようです)。早朝の濃飛高山車庫には、濃飛車輌のほかに、京王、近鉄、名鉄の車輌が居ることになります。
また、「トイレ付き車輌」は、(私の説が正しければ)1日に新宿線3両、大阪線2両、名古屋線3両の計8両が使用されるわけですが、車輌自体も22-15を含めても8両で、かなりきつい運用になっているようです。新宿線や大阪線の高山帰着車輌をそのまま次の同線の運用に投入することは物理的には不可能ではありませんので、その辺でうまくやっているのでしょう。いずれにしても、車輌運用担当の方の苦労がしのばれます。早く、増備車がほしいですね。
と言っていたら、平成15年6月に200-76が増備されたようです。同車は、同年に導入された観光用車輌と同様の「低公害バス」のようです。
時刻表と向き合うと、このようなことも見えてきて、楽しいものです。
○上へ ○興味をひく運用 ○時刻表 ○説明 ○濃飛バスIndex ○総Indexへ戻る
[Your Position]
Sami's HOMEPAGES MAIN INDEX > 濃飛バス
INDEX > 「興味を引く運用」
> 「濃飛高速路線の車輌と運用」
Internet
Explorer 4.0以上のご利用をお勧めします。
著作権情報 ©2014 O.K. All rights
reserved.
最終更新日:14/03/29